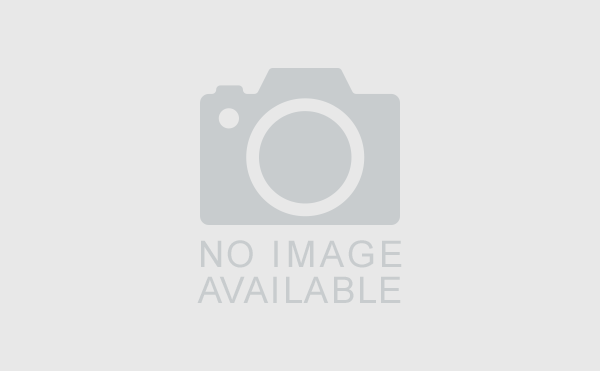現金はゴミか?(1)米ドルの待機資金はどこに置いておけばいい?
長めのデュレーションの債券投資において、実質金利の変動に対処するのは容易ではない。
しかし、インフレならば、一応、物価連動国債(TIPS)という投資対象がある。
クーポン金額や償還金額がCPIに連動する国債だ。
TIPSに投資すれば、インフレの上下については免疫を持つことができる。
ちなみに先月末のTIPS利回りは5、7、10年についてそれぞれ1.48%、1.72%、1.95%だった。
インフレ(CPI)が上下しても、これだけの実質ベースの増価が得られるということ。
MMFや名目債との違いは、MMFや名目債ならインフレによる変動のリスクを投資家が取ることになる。
TIPSなら発行体(米国政府)が取ってくれるので、投資家は一応インフレについてクヨクヨ考えないで済む。
こちらの方がいいと考える人もいるのかもしれない。
ちなみに、決して推奨するわけではないが、日本の証券会社でも扱っていそうな米ETFとしてはTIP、SPIP、VTIPなどがあるようだ。
前2つは長め、最後は短めのデュレーションになっている。
コストもそう大きくなさそうだし、インフレ・ヘッジの手段の1つになるかもしれない。
しかし、ここでもまだ2つほど課題が残る。
- TIPSはインフレをヘッジするが、実質金利の変動(主に上昇)をヘッジはできない。
- リスク資産下落時に有利な価格でExitできるのか。つまり、待機資金の置き場所として適当か。
実はこの2つの課題は同じところに根差した課題なのだと思う。
過去の弱気相場で物価連動債はどう変動したか
そこで、過去のTIPS価格の挙動を振り返ってみたい。
- TIPS価格: TIPで代用。デュレーション6.35年
- 米名目債価格: IEFで代用。デュレーション7.05年
- 米株価: S&P 500
まず、コロナ・ショックが襲った2020年を振り返ろう。
米TIPSファンド(青)、米国債ファンド(黒)、S&P 500(赤) (コロナ・ショック前後)
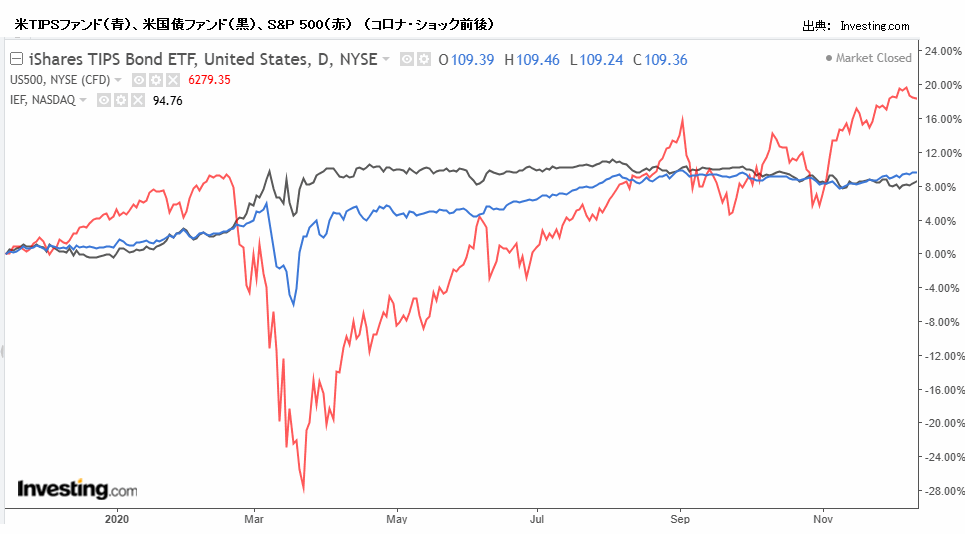
コロナ・ショックによる米株価急落は2020年2月下旬に始まった。
当時のTIPS(青)、名目債(黒)を見ると、しばらく上昇しているのがわかる。
この短期間、TIPSと名目債は立派に分散効果を発揮したのである。
その後、3月上旬にいくらか動揺が走った後、名目債は逆相関とはいかなかったものの、価値の保全という役割を果たしている。
TIPSも全体で見ればまあまあの働きをしたのだが、3月上旬からの下落がやや大きく、その後の回復にも少々時間がかかっている。
3月上旬には何があったのかと言えば、FRBの緊急利下げである。
この月、FRBは3度の緊急FOMCを開催、加えて2度の投票をともなうリリースを行い、利下げと資産買入れ等を実施している。
株価下落後3月上旬まで債券価格が上昇したのには3つの解釈がありえよう。
- 株が売られ、債券が買われた。
- 市場が金融緩和を先取りした。《Buy the rumor, sell the fact.》
- 当時はまだインフレが顕在化していない時代であり、コロナ・ショックがデフレ的ショックであると解釈され、金利が下がった。
前2つは、市場の振る舞いとしてかなり一般的な部類に入るだろう。
一方、最後の1つは、必ずしも再現を望めないかもしれない。
世界がインフレの時代に入ったかもしれないからだ。
ちなみに、3月上旬以降、TIPSが少々下げている。
1つの解釈は、デフレ懸念を反映したものというものだろう。
名目債価格が比較的安定していた、つまり、名目金利が安定していた中で、コロナ・ショックによるデフレ/ディスインフレ懸念が高まったのだろう。
その後、その懸念が解消したのは、米国のブレークイーブン・インフレ率にもはっきりと表れている。
米国のブレークイーブン・インフレ率(BEI)
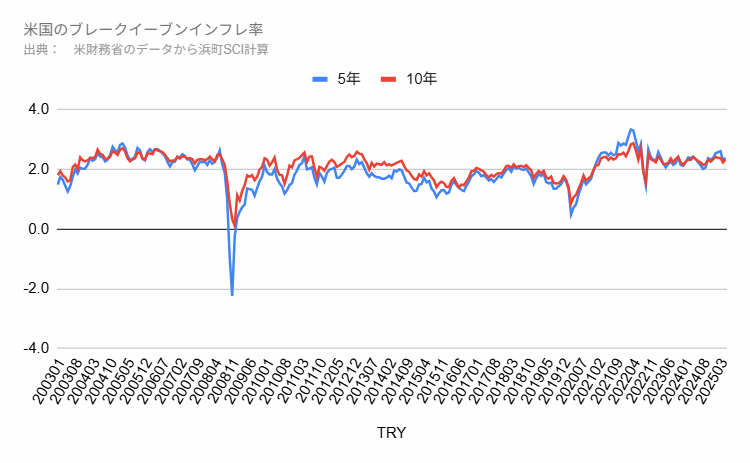
(次ページ: インフレの世界ではTIPSはどうなる?)