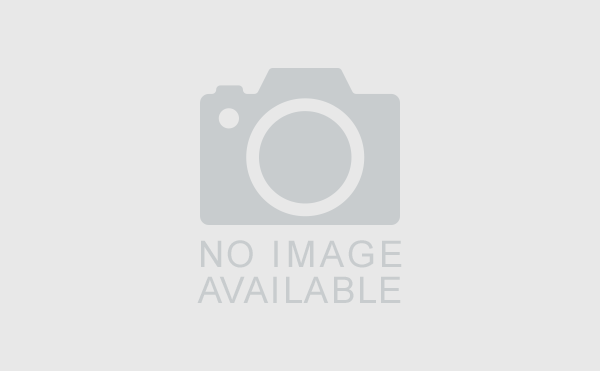名目債、物価連動債、変動金利債。日本の物価連動債の魅力がイマイチな本当のワケ
最近、物価連動債について何度か触れたが、この分野について必ずしも投資家の理解度は高くないようだ。
財政問題に起因するインフレリスクが心配される中、物価連動債への期待が高まっているが、投資検討の前に何がヘッジされ何がヘッジされないか正しく理解することが大前提だ。
まず最初に理解しなければいけないのは、私たちが日ごろ《金利》と呼んでいるものは、厳密に定義すると《名目金利》であるということ。
例えば金利(名目金利)が1.5%の投資があっても、インフレが3.3%なら、価値の変化はマイナスに終わってしまう。
インフレ調整後(インフレ分を差し引いた)の金利を《実質金利》と呼び、先ほどの例なら-1.8%になる。
ここでは信用リスクなどを無視するため国債を取り上げ、クーポンの決まり方から3タイプを紹介する:
- 名目債: 一般的な(名目)固定金利の国債。
- 物価連動債: クーポン(定期的利払い)や元金償還額がインフレ(全国のコアCPI)に連動する国債。
- 変動金利債: クーポンが基準金利に連動する国債。例えば個人向け10年だと10年もの名目債の新規発行利回りに掛け目を掛けた金利で変動する。
この3つの違いを理論的に理解するには、最も単純なフィッシャー方程式:
名目金利=実質金利+期待インフレ率
を想定するとよい。
誰が実質金利とインフレのリスクを受け持つか?
実質金利と物価が変動する負担を誰が受け持つかを整理しておくとよい:
| 実質金利変動リスク | インフレリスク | |
| 名目債 | 投資家 | 投資家 |
| 物価連動債 | 投資家 | 発行体(政府) |
| 変動金利債 | 主に発行体(政府) | 主に発行体(政府) |
早合点しないでいただきたいのは、変動リスクの負担を逃れることイコール善とは限らないということ。
リスクを負担することがリターンを生みうるというのが金融市場の常だ。
変動金利債では発行体が実質金利・インフレ両方のリスクの大部分を負担する。
その見返りに発行体は金利を安く(つまり掛け目を掛けること)することができている。
(厳密には、ターム・プレミアム分が逆に効いているとの解釈もありうる。)
誤解から来る物価連動債への過度な期待
物価連動債では、政府は無償でインフレリスクを負ってくれている。
これは一見、投資家にとってお得なように見えるが、そうとは限らない。
お得に見えるから物価連動債が好まれ、買われ、結局は利回りがその分低くなる。
実際、日本の物価連動債利回りは5-10年レンジでマイナス圏にある。
(ただし、10年はほぼゼロに近い水準。)
新発債を買おうが、既発債を買おうが、利回りはマイナスなのである。
また、物価連動債について多い誤解は、投資信託商品でしか個人が買えないから魅力がないというもの。
もちろん投資信託にともなうコストは重要なポイントだが、それは1つの要因でしかない。
仮に個人が現物債を買えるようにしても、現状のマイナス利回り水準では魅力があると捉える人はそう多くないだろう。
(次ページ: 債券価格は変動する。債券投資の考え方)