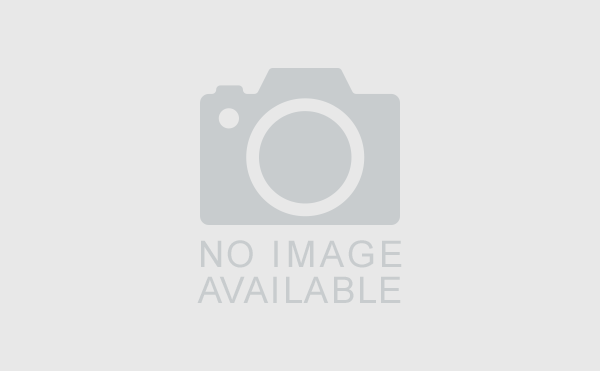名目債、物価連動債、変動金利債。日本の物価連動債の魅力がイマイチな本当のワケ
おそらく、名目債と変動金利債ではリスク負担のあり方が相対的にはっきりしているため、理解しやすいのだろう。
問題は、名目金利分の一部であるインフレだけをヘッジした物価連動債の考え方だ。
物価連動債でも意識すべき実質金利変動リスク
物価連動債において実質金利についてヘッジされていない点をどう理解すればよいか。
それは、実質金利の上昇要因を例示すればイメージしやすい。
- 経済の潜在成長率が向上し資金需要が高まる場合: そうそうあることではなく、長い時間をかけて起こるか、長い時間の中で断続的に起こるものだろう。
- 中央銀行の利上げ: 特にイールドカーブの長期側で上昇が許容される(量的緩和解除・量的引き締め)と中長期投資に影響が及ぶ。
- 国内投資家の国債売り: 何らかの理由で国内投資家が国債を売れば、実質金利が上昇する。
- 国内投資家の海外投資・海外投資家の国債売り: 実質金利上昇とともに円安の要因となり、これがインフレ要因となる。
1. 経済の潜在成長率が向上し資金需要が高まる場合
物価連動債だけを見れば下落要因となろうが、投資全体で見れば悪いことではない。
そもそもそうそう急激に起こる変化でもない。
それ以外のシナリオは少し心配すべきだろう。
2. 中央銀行の利上げ
この先、中央銀行がさらに金融政策を引き締めたり、極端な緩和からの正常化を進めると思うなら、物価連動債にも脅威になる。
逆に、中央銀行が(景気後退などで)利下げに動くなら、チャンスになる。
景気後退時、デフレなら名目債でメリットが大きく、スタグフレーションなら物価連動債でメリットが大きい。
3. 国内投資家の国債売り
例えば、国内投資家が預金・債券を取り崩すなどして直接・間接に国債に売り圧力が加わるなら、物価連動債にも脅威になる。
4. 国内投資家の海外投資・海外投資家の国債売り
3と同様、物価連動債にとって脅威になるが、このシナリオでは円安・インフレ進行が共存しうる。
物価連動債ではインフレはヘッジされるが、インフレより円安が過酷なものになると、円安による悪影響は残るかもしれない。
日本の物価連動債でヘッジされるのは、コアCPI、つまり生鮮食品を除く総合指数の部分までだ。
日本の物価連動債の魅力がイマイチな本当の理由
日本でも物価連動債は必須の品揃えだと思うが、決して諸手を挙げて買いに行くような利回りでもない。
魅力があまり高くない理由は明らかだ。
それは日本がまだ金融緩和を継続しているからだ。
(もちろん、それなりの理由があるから継続されている。)
仮に金融政策の正常化が実現されれば、物価連動債の利回りも魅力が高まってくるはずだ。
(実際、米国では金融は引き締め的であり、物価連動債利回りも2%を超え、魅力が高まっている。)
そして再度、リスクを負担すればリターンが得られる場合がある点を強調しておく。
金融市場にフリーランチは存在しないことを忘れてはいけない。
物価連動債利回りが魅力的になるということは、名目債や変動金利債でも利回りが魅力的になっていくということ。
皮肉なことに、利回りが魅力的になる原因の多く(上記2から3)は、国債が売られる、つまり国債の魅力が減ることによるものになりがちだ。
今、物価連動債を切望している人の多くは、物価連動債の利回りが魅力的になったからと言って、物価連動債を買おうとはしないだろう。
物価連動債価格が下落しているのを目の当たりにし、買う気が失せてしまうからだ。
賢明なる投資家とは、そういう時にも買いを検討できる人だ。
価格が変動しようが、利回りが変動しようが、物価連動債を買う理由は常に存在する。
それは、ポートフォリオ分散に寄与するという点。
債券の魅力とは利回りの高さ・安さだけで測るべきではない。
その最大の魅力の1つは、ポートフォリオの分散にどれだけ寄与してくれるかにある。
そもそもの話、高い利回りが欲しければリスクカーブを昇っていくしかない、というのがファイナンス理論の前提だ。
高い利回りが欲しければ、より高リスクの資産クラスを検討する方が現実的だ。
そして、それと組み合わせるのにどの低リスク資産を選択するか、がポートフォリオ運用であろう。